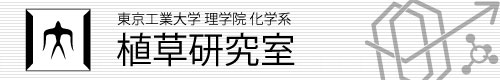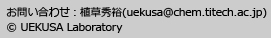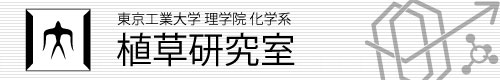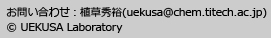研究設備
研究室の設備を紹介します。
測定装置
分析装置
|
Rigaku ThermoPlus Evo
熱分析装置。熱重量分析(TG)、示差熱分析(DTA)、示差走査熱量測定法(DSC)が行える。
結晶の相転移や溶媒の脱着などを調べるのに大活躍。
|
合成設備
|
実験テーブル
こんな感じの実験テーブルが部屋の中央に二台。
|
|
ドラフト
実験室内に溶媒の蒸気が拡散しないように吸気する実験用装置。
|
解析環境
パソコン
1人1台のPCと、デュアル・ディスプレイを使用可能。
解析(他)用の共有端末が1台。
共通のX線回折装置
化学系共通のX線回折装置
|
Rigaku VM-SPIDER
集光ミラーVariMaxCuを搭載したRAPID2。
CuKa線を集光しているので超強力な(輝度の高い)X線が出る。
2008年導入。微小結晶でも測定可能。
|
|
Rigaku XtaLAB mini
卓上型の単結晶X線回折装置。
0.3mm角の結晶であれば,2〜3時間で測定することができる。
|
|
Rigaku SmartLab
光学系の自動調整機能、CBO(Cross Beam Optics)に対応したインテリジェントな粉末X線回折装置。結晶相の同定や結晶化度の評価だけでなく、粉末未知結晶構造解析にも利用可能な高分解能データを測定できる。
|
学内共用のX線回折装置
|
Rigaku XtaLAB Synergy-DW
Mo/Cu2波長線源を搭載した高輝度X線発生源と高速HPC検出器を組み合わせた最先端の単結晶X線回折装置。超高速回折計と高機能統合解析ソフトウェアCrysAlisProのシナジー効果により、モノによっては10分以内に測定が終わることも。
|